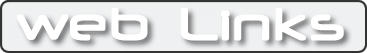リンク
RSS/ATOM 記事 (61996)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


|
米Verve社、心血管領域のin vivoゲノム編集療法の開発でLilly社と提携
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-28 7:00)
|
米Verve Therapeutics社は2023年6月15日、米Eli Lilly社と独占的な研究協力契約を結んだと発表した。目的は、Verve社が前臨床開発を進行中の、リポ蛋白(a)すなわちLp(a)を標的とするin vivo遺伝子編集プログラムの開発推進にある。
|
|
米Coherus社、がん免疫抗体医薬を複数保有する米Surface社を92億円で買収
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-28 7:00)
|
米Coherus BioSciences社は2023年6月16日、米Surface Oncology社を買収する契約を締結したと発表した。Surface社が臨床開発中のがん免疫抗体医薬など複数品目を獲得し、がん免疫療法の開発パイプラインを強化する狙いだ。買収総額は6500万ドル(約92億円)に達する可能性がある。同契約に伴う取引は両社の取締役会が全会一致で承認した。
|
|
クオリプスが上場、初日の時価総額は99億円
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-28 7:00)
|
他家iPS細胞由来心筋細胞シートを開発しているクオリプスが2023年6月27日、東証グロースに上場した。初値は公開価格の1560円を7.7%上回る1680円を付けた。一方で、終値は1312円で、上場初日の終値ベースの時価総額は約99億円だった。2023年のバイオスタートアップの上場は、同社が1社目となる。
|
|
JSR、JIC関連会社によるTOBで、どうなるライフサイエンス事業
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
官民出資の投資ファンドである産業革新投資機構(JIC)は2023年6月26日、完全子会社のJICキャピタルが子会社であるJICC-02を通じて化学素材大手のJSRの株式などを公開買い付け(TOB)で取得すると発表。これに対してJSRは、同日開催の取締役で全会一致で賛同の意見を表明すると共に、株主に対してTOBに応じることを推奨すると決議した。JSRのEric Johnson CEO(最高経営責任者)は同日会見を開催し、その理由などを説明した。
|
|
レボルカ、住友ファーマとの共同研究で医薬品候補蛋白質の取得に成功
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
AI(人工知能)を用いた蛋白質設計を手掛けるレボルカ(東京・中央、片岡之郎代表取締役社長)は2023年6月23日、住友ファーマとの共同研究で、治療薬候補となる蛋白質(開発番号:RK003)を取得したと発表した。RK003については今後、住友ファーマが研究開発を担う。また、レボルカは住友ファーマとの共同研究契約に基づき、マイルストーン収入を受け取った。マイルストーンの金額は非公開だ。
|
|
英Quell社とAZ社、1型糖尿病と炎症性腸疾患を適応にTreg療法の開発提携
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
制御性T細胞(Treg)の改変技術を保有する英Quell Therapeutics社は2023年6月9日、英AstraZeneca(AZ)社とTreg細胞療法の共同開発とライセンスに関する契約を締結したと発表した。Quell社はAZ社から契約一時金8500万ドル(約119億円)を受け取り、1型糖尿病(T1D)と炎症性腸疾患(IBD)を適応とする開発プログラムに着手する。
|
|
米Alladapt社、食物アレルギーの複数抗原経口免疫療法が第1/2相試験で好結果
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
IgE依存性食物アレルギーに対する治療を開発している米Alladapt Immunotherapeutics社は2023年6月13日、複数抗原を利用した食物アレルギーの経口免疫療法であるADP101の有効性と安全性を評価する第1/2相Harmony試験で、好結果が得られたと発表した。データは、2023年6月9〜11日にドイツで開催された欧州アレルギー臨床免疫学会で口頭発表された。
|
|
パイプライン研究◎前立腺がん治療薬【開発動向編】、前立腺がん治療薬、アステラスが「イクスタンジ」の適
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
前立腺がんでは、男性ホルモンであるテストステロンの刺激が腫瘍を成長させる。このため、代表的な治療法は、男性ホルモンが主に生成される精巣において、テストステロン生成を阻害することだ。治療薬としては「リュープリン/Lupron(ルプロン)」(リュープロレリン、武田薬品工業/米AbbVie社)や「ゾラデックス」(ゴセレリン、英AstraZeneca社)などの性腺刺激ホルモン放出ホルモン受容体作動薬が広く用いられてきた。
|
|
特集◎実験自動化の現在地【後編】、創薬・化学・再生医療の現場に学ぶ、自動化の活用例
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
製薬企業や化学企業などが、研究や製造の一部工程を自動化している。背景には、実験量の増加や作業時間削減などの需要の高まりがある。複数の自動化装置を組み合わせて使ったり、細胞培養などの複雑な作業を自動化したりすることも可能になった。バイオ業界における実験自動化の現在地を探った。特集後編では、アステラス製薬、中外製薬、カネカ、エーザイの各企業での実用化例に加え、神戸市立神戸アイセンター病院での再生医療に自動化装置を導入した事例から、自動化装置の活用法を学ぶ。
|
|
ダイダン子会社、再生医療等製品の製造業許可を取得しCDMO事業に参入
from 日経バイオテクONLINE
(2023-6-27 7:00)
|
空調や電気などの設計・管理・施工を行うダイダンの子会社であるセラボヘルスケアサービスは2023年6月21日、記者会見を開催し、細胞培養加工施設(CPC)「セラボ殿町」で、細胞医薬の開発製造受託(CDMO)事業を開始すると発表した。同社は2023年5月にセラボ殿町における再生医療等製品の製造業許可を取得。今後、九州大学発スタートアップのガイアバイオメディシン(東京・新宿、倉森和幸代表取締役CEO)の治験製品(GAIA-102)を製造する。
|