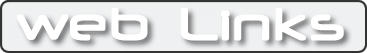|
国立科学博物館 産業技術史講座
from --Online ROBOCON Magazine--
|
日本の工業化住宅の変遷
第二次大戦後、世界的に住宅不足解消のためプレハブ住宅の研究や起業が行われたが、日本だけが、特に低層住宅のプレハブ化に成功し大きな産業として発展した。
多くの試練があったがさまざまな努力で乗り切り、日本の住宅のリーダー的役割を果たすようになった、その変遷を概観する。
また、工業化住宅の性能住宅としての特徴についても、その一部を平易に解説する。
■日 時
平成22年(2010年)12月11日(土) 14時〜16時(開場 13時30分)
■会 場
国立科学博物館(上野) 地球館 3階講義室
■講 師
東郷 武(前・産業技術史資料情報センター・主任調査員)
■募 集
40名(高校生以上一般向)
■入館料
入館にあたり、下記の通常入館料が必要です。
一般・大学生 600円
高校生・満65歳以上の方は無料(年齢が分かる証明書等を提示)
■申込方法
往復はがきもしくは下記ウェブサイトからお申し込みください。
平成22年(2010年)11月20日締切(消印有効)
http://sts.kahaku.go.jp/diversity/lecture/index.php
国立科学博物館 学習企画・調整課 学習支援事業担当
〒110-8718 台東区上野公園7- ...
|
|
ロボット工学セミナー「屋外における自律移動技術」
from --Online ROBOCON Magazine--
|
日本ロボット学会主催の「屋外における自律移動技術」(10月29日開催)につきまして,ご案内させていただきます.
http://www.rsj.or.jp/events/Seminar/2010/RSJ_Sympo_60.htm
本セミナーでは,以下の気鋭の先生方をお招きして御講演頂きます.
1. 屋外移動ロボットにおける自律移動技術(総論)
筑波大学 坪内 孝司 氏
2. 自動車の運動力学と制御 運動方程式 運動性能と制御
日本大学 堀内 伸一郎 氏
3. 屋外自律移動のための視覚環境認識
豊橋技術科学大学 三浦 純 氏
4. 屋外での環境センシング技術を用いた3次元地図生成
早稲田大学 石川 貴一朗 氏
5. 自動車の安全を支える画像認識技術
日立製作所 志磨 健 氏
近年,掃除ロボットや警備ロボットをはじめとした移動ロボットの活躍の場は,屋内から屋外施設,そして市街地へとますます拡大してきています.一方で,屋内に比べると,屋外における広範囲の移動では,移動制御,センシングともに,屋外環境に対する高いロバスト性を求められます.本セミナーでは,屋外自律移動の研究をこれから始めようとする方々や既に研究を進めている方々の一助となるよう,屋外自律移 ...
|
|
Make: Tokyo Meeting 06が東工大にて開催!
from --Online ROBOCON Magazine--
|
オライリー・ジャパン主催の、ナイスでグッドなガジェットが大集合する、「Make: Tokyo Meeting 06」が下記の通り開催されます。
自慢のガジェットを持ち寄るもよし、アイデアをいただきにいくのもよし、楽しいイベントなので、一度足を運んでみてはいかがだろうか。
■ 開催日
2010年11月20日(土)、21日(日)
■会場
東京工業大学 大岡山キャンパス(東京都目黒区大岡山2-12-1)
※東急大井町線、目黒線「大岡山駅」徒歩1分
■主催
株式会社オライリー・ジャパン
■共催
東京工業大学、多摩美術大学 情報デザイン学科
■参加費
無料
■出展申し込み
下記のフォームからお申し込み下さい。
http://jp.makezine.com/blog/2010/09/mtm06_entry.html
■その他
Make: Tokyo Meeting 06に関する公式ハッシュタグは#mtm06です。その他詳細は随時発表します。
■問い合わせ
担当:田村(tamura[at]oreilly.co.jp)※[at]を@に置換えて下さい。
Make: Tokyo Meeting 06
http://jp.makezine.com/blog/2010/11/mtm06_announce.html
|
|
ロボットの作り方(センサ・マイコン編)
from --Online ROBOCON Magazine--
|
■主催
先端ものづくり・まちづくり協議会(CATTOM)
■後援
習志野商工会議所
■日時
2010/11/17(水) 9:30-16:00
■場所
千葉工業大学津田沼キャンパス
■費用
CATTOM会員:20,000円/非会員:25,000円(ロボットキット代などを含みます)
※当日現金でお支払いください
■定員
20名(定員になり次第締め切らせていただきます)
■講師
青木岳史(千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科准教授)
■内容
マイコンを用いたロボットの動かし方、プログラムの実際を学び、マイコン周りの電子回路作成などを行います。電子工作・プログラムといったロボット製作の基礎を、実習を通して実際に学ぶことができます。
■申込み方法
電子メールにてH.Minakata(at)gmail.com((at)は@に置換えて下さい)まで「ロボットの作り方11/17分申込」と記載してお送りください。電子メールが使えない場合は、FAX:047-476-9708(CATTOMサブオフィス)を利用ください。
※2、3日中に確認のメールを返信いたします。メール返信のなかった場合は047-478-0369南方(ミナカタ)までお問い合わせください。
■注意事項
・当日は、実習の際の妨げになりそうな服装・履き物などはご遠慮下さい ...
|
|
アーチェリーをするロボット
from --Online ROBOCON Magazine--
|
こんにちは、編集長です。
イタリアの国立研究所所「Italian Institute of Technology (IIT)」の Dr. Petar Kormushev と Dr. Sylvain Calinon、Dr. Ryo Saegusa が、ヒューマノイドロボット「iCub」にアーチェリーを習得させたそうです(編集部にご連絡をいただきました!ありがとうございます)。
アーチェリーをするロボット「iCub」です。
YouTubeで 「Robot Archer iCub」 という動画が公開されています。
ちゃんと弓を持って、矢をつがえているのですが、最初は全く的に当たりません。それが何回も的を狙って、矢を撃つことを繰り返していくとだんだん的に当たるようになって、8回目では的の中心に当てています(鏃が吸盤なので、うまくくっつかなかったのが残念)。これは偶然に成功したわけではなくて、iCubが学習しているんですね。
「iCub」は身長が104cmで、自由度が53。的との距離は3.5mだそうです。 Dr. Petar Kormushev のホームページ (英語)でこの実験の解説があります。iCubのアーチェリートレーニングのためのアルゴリズムについても簡単に説明してくださっています。時間があるときに辞書と首っ引きで読んでみたいと思いますが ...
|
|
ブラックリスター
from --Online ROBOCON Magazine--
|
こんにちは、編集長です。
いつもより1時間早く起きたら、今になってものすごく眠いです...
さて、9月20日に「 ブラックリスター 」という映画の試写会に行ってきました。
ストーリーは、借金を重ねて返済が出来なくなり、ブラックリストに掲載された4人の「ブラックリスター」が、賞金3億円をかけてロボットバトルを繰り広げるというものです。
このゲームを運営する事務局と契約して、支給されたクレジットカードを使ってロボットを手に入れるのですが、その支払いは自分持ち。ただし、1位と2位は利用代金は事務局持ちとなる特典がつきます。ただし、契約違反があれば違約金5000万円を支払うことになります。結構な崖っぷち状況から誰が勝ち残るのでしょうか...といった感じです。
二足歩行ロボットによるバトルなのですが、CGではなくて実機を使用。 ROBO-ONE に参加しているロボットが出演しているので、それらによるバトルが繰り広げられます。
監督は ROBO-ONE ENTERTAINMENT 事務局も担当し、ROBO-ONEの会場演出を担当している株式会社ロクスリーの渡邊豊さん。ちなみに企画・原案・脚本も担当しています。制作費などは関係者の ...
|
|
電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト2010
from --Online ROBOCON Magazine--
|
ヒト型レスキューロボットコンテストとは、1999年から毎年開催されている「レスキューロボットコンテスト」の新たな展開を目指し、ヒト型ロボット1 台と操縦者1名で参加できるロボット競技です。今回の競技では、ヒト型ロボットを目視で遠隔操縦して、3.6m ×2.0mのフィールド内で「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」の四つのタスクを順にクリアし、かかった時間の短さを競います。また、要救助者搬送に関しては、審査員による「やさしさ」の評価が加わります。要救助者には、身長320mmのデッサン人形を用います。
レスキューロボットコンテストは、ロボット競技を通じて、ものづくりの楽しさを伝えるとともに、防災や減災の大切さや難しさを考える機会を提供しています。本コンテストも、この考えを受け継ぎ、さらに多くの皆さんに輪を広げるために開催します。今回は、昨年に引き続き2回目の開催です。前回の経験を踏まえて、参加者と一緒になって新しい競技を検討していきます。
日時:2010年11月7日(日)
10:00-12:00 ミーティング、ロボット検査、試走
12:00-17:00 競技
場所:大阪電気通信大学 寝屋 ...
|
|
電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト2010の募集開始
from --Online ROBOCON Magazine--
|
こんにちは、編集長です。
新着ロボコン情報 にも掲載しましたが、「電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト」が11月7日に行われます。その参加者募集が開始されています。ちなみに2009年大会の記事は 2010年1月号 に掲載されていますので、そちらをご参照いただければ。
さて、ヒト型レスキューロボットコンテストは、以下のような競技内容になります。
「ヒト型ロボット1 台と操縦者1名で参加できるロボット競技です。今回の競技では、ヒト型ロボットを目視で遠隔操縦して、3.6m ×2.0mのフィールド内で「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」の四つのタスクを順にクリアし、かかった時間の短さを競います。また、要救助者搬送に関しては、審査員による「やさしさ」の評価が加わります。要救助者には、身長320mmのデッサン人形を用います。
昨年の大会は、ROBO-ONEやロボファイトなど、二足歩行ロボットの大会の参加経験者も多くいましたね。
申込は、「 電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト2010 」のホームページにあるる募集要項と競技規定を読んだ上で、所定のファイルを電子メールに添付して送ります。 ...
|
|
可児工業高等学校に行ってきました
from --Online ROBOCON Magazine--
|
こんにちは、編集長です。
今週は、実は月曜日に岐阜まで行っていました。8月に開催された、ルネサスマイコンカーラリー競技会で優勝した「テスタープロト」について、いろいろお話しを伺いに行ったのです。
名鉄の新可児駅からタクシーに乗ったときに、運転手さんに「暑いでしょう」と言われましたが、正直なところ、東京とほっとんど変わりませんでした。空気がよどんだ感じがしないだけマシかもです。
さて、目的は「テスタープロト」の撮影だったり、コンセプトやどんなふうに製作していますか?というインタビューが中心だったのですが、そもそも、可児工業高等学校電気システム部は高校生以下の部の優勝と準優勝を勝ち取ったチームでもあります(「テスタープロト」の製作者である深澤先生は顧問、高校生以下の部で優勝した「テスターツボイ」の坪井さんと、準優勝の「テスターシャックリー」の神谷さんは部員です)。
なので、可児工業高等学校電気システム部の活動についてもお話しを伺ってきました。意外と体育会系だったりとか、段階をふんで学んで行ったりしているところとか、結構面白かったですね。いろんな勉強会を自ら開いたり、校内で使える ...
|
|
HRP-4
from --Online ROBOCON Magazine--
|
こんにちは、編集長です。
TXのつくば駅改札前にあるつくばの物産品などを売っているお店で、ミニトマト(超ミニ)と大根の甘酢漬けを買ってしまいました。
今日は産総研に行ってきました。「HRP-4」の発表会です。HRP-4というと、昨年発表された「HRP-4C」を思い出す方も多いと思いますが、今回は女性型ではありません。
コンセプトは「スリム・アスリート」で、陸上選手のような引き締まった筋肉質の働くロボットのイメージだそうです。頭部のヘルメットのように見える部分は、なんとなくアメフトの選手を思い出させますねえ。
「HRP-4」。ちなみにこれが「決めポーズ」だそうです(音声コマンドで「決めポーズ」というと、このポーズをしました)
「HRP-4」と「HRP-4C」。
「HRP-4」は 川田工業 と 産総研 が共同で開発した、働く人間型ロボット研究用プラットフォームです。身長が151cm、重量が39kgと軽量でスリムなボディーです。HRP-2、HRP-3と並べるとその大きさがよくわかります。
左から「HRP-2 Promet」、「HRP-3 Promet MarkII」、「HRP-4」。
デモは、体操動作や、両手先で円を描く動作、後ろを向いて、かつ ...
|